乙部町姫川には、同じモチーフで細部が異なる伝説が、いくつか残されている。
乙部姫川ver.1
乙部町、姫川には、源義経に会えなかった静御前が身を投じたといわれている伝説がある。そのために姫川と名づけられた。
また、この川の上流にある姫待峠は、義経が静御前を思いつつも越えなければならなかったことで命名されたという。
乙部姫川ver.2
昔、この川の上流からお姫様が現れたので、この名がついた。
このお姫様は、川の上流からお供の者に連れられてやって来て、ボロボロの着物を着ていたが、立ち居振る舞いから身分の高い人と想像されたという。同情した村人が、川に上った鮭を松前藩に献上し、いただいたお金がお姫様の衣装代や化粧代になったという。
森町の姫川
森町にも「姫川」という地名がある。ここにも伝説が伝わっている。戦に破れたお姫様を連れた武士が、お姫様を箱詰めにして川へ流すことにした。流れ着いた所で山に入り、洞穴で暮らすようになったという。川の上流に美しいお姫様が住んでいたので、姫川と名づけられたという。
レポートと解説
乙部町の姫川の名は、昔この川に上味屋と下味屋(味屋とは秋味つまり鮭屋さん)とがあって、この鮭の運上料(税金)が代々松前藩の姫君のお化粧料として徴収させられたため、というのが本当のところらしいです。
また、乙部岳は義経の別名「九郎判官」から九郎岳とも呼ばれています。
この二つの伝説には「どこからか逃げてきたお姫様」というキーワードがあります。そこで、このお姫様とは、駒ケ岳伝説に出てくる相原季胤が逃がした(伝説では入水したことになっている)二人の姫が森町と山を越えた乙部町に、逃げのびたのではないかと推測する説もあります。
[google-map-v3 width=”350″ height=”350″ zoom=”12″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”false” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”41.969344,140.186754{}textiles.png{}姫川・姫待峠:乙部町” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]
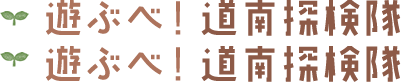



コメント