 函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説 縁桂:乙部町
「縁結びの神が宿る」と伝えられる樹齢約500年の大木。1本の木の枝が別の木の幹に地上7メートルのところで絡み、1本になった。この木に触ると縁が結ばれると地元の人々に崇められている。明治の終わりごろ荒木万太郎という豪傑の漁師がいた。親方の船を...
 函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説  函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説  函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説 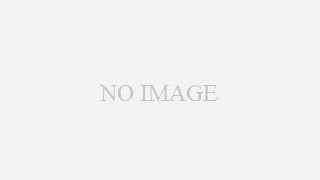 函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説  函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説  函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説  函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説 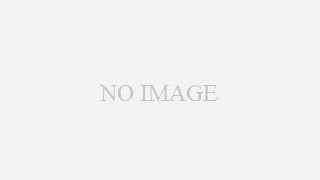 函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説  函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説  函館・道南の歴史・伝説
函館・道南の歴史・伝説